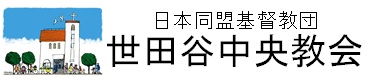「2つのたとえ」
2025年9月7日 主日礼拝説教梗概
聖書:ルカの福音書18章1~14節
説教:安藤友祥主任牧師
イエス様は、裁判官とやもめ、パリサイ人と取税人、二つのたとえを通して、祈りの姿勢について。そして、神様に義とされる人について教えられています。
1つめのたとえに出てくる裁判官は、第二歴代誌に書かれている町のさばきつかさの正反対のような人物です。もう一人の登場人物、やもめは、社会的に弱い立場にあり、訴えられるときに、彼女を弁護してくれる人の姿も見えません。イエス様はこの神様と似ても似つかない裁判官と神様を並べて教えます。不正な裁判官でもそうなのだから、神様はなおさら祈りに答えてくださる。日夜熱心に祈る祈りを聞いて、正しいさばきをしてくださると祈る事を励まします。ここでイエス様は信仰者たちの人の子の日を待ち望む祈りに関して教えられていることに気が付きます。なかなか来ない人のこの日。与えられない神様からの解決。人々はやがてその解決が無い状況の中、諦めたり、祈れなくなったりしてしまうかもしれません。だからこそイエス様は1節の言葉を言われたのです。
2つ目のたとえですが、パリサイ人の祈りは、彼は「神様」と呼びかけてはいますが、自分自身の正しさ、行いに目を向けています。そして、取税人の様ではないと他人と比較して、自分の正しさを主張します。パリサイ人は祈っているようで、自分の義を認めてもらいたい。自分は神様の目から見て義であると、自分で判断をしているとも言えます。対して取税人は悔い改め神様に憐れみを求める。イエス様はこの二人で義とされたのは取税人だと教えます。パリサイ人は人を見下し、自分を義としてしまっていました。何より、彼の祈りの言葉を見る時に、神様に何も求めていないことに気が付きます。彼は本当の意味で神様を必要としておらず、神様の助けも必要としていません。そのような生き方は義とされないのだと。ただ自分の罪を自覚し、神様の憐れみが、神様の助けが必要だと、へりくだり、神様の義を求めるもの、そのように神様の前に立つものが、義とされるのだと教えられます。人と比べて自分が上だと思う時、残念なことに、そこには優越感と同時に、安心感もあります。けれどもそうではなく、私たちは人と比べて、自分を義とする偽りの安心感、自己義認から解放されるものでありたいのです。罪の影響が与える、比べて生きる不自由さから解放をいただきましょう。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 説教梗概2026年2月1日「神の測り方」
説教梗概2026年2月1日「神の測り方」 説教梗概2026年1月25日「カエサルのもの、神のもの」
説教梗概2026年1月25日「カエサルのもの、神のもの」 説教梗概2026年1月18日「神の子どもである恵み」
説教梗概2026年1月18日「神の子どもである恵み」 説教梗概2026年1月11日「イエスの権威」
説教梗概2026年1月11日「イエスの権威」